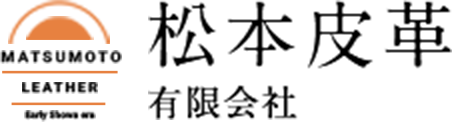2020年6月
- 新着情報
-
あなたのための革を小さくお作り致します。
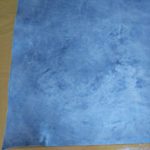

写真は例ですが、お客様のご要望をお聞きして、革をあなたの色に染めさせて頂きます。
大きさ・・・A4大(6デシ)~60デシ(半裁革の1/4くらい)程度まで。一枚から可。
ご希望の革部位、ご相談させて頂きます。部位によってはお安く加工できます。
お値段・・1デシ95円~110円程度。革代、加工費を含みます。
染め方・・・染料による丘染め(ヌメ革)、もしくはクロム革(芯通し黒)への顔料塗装。
染料にパール等の顔色でうすくコート等もできます。
ヌメ革はオイルにて柔軟処理します。
申し訳ありませんが芯通し染めは、現在承っておりません。
表面加工・・・染料染色は被膜薄めでポリウレタン樹脂コート致します。顔料は若干被膜が厚めになります。
アイロン加工にて光沢処理も致します。
漉き加工・・・無償。0.8ミリ程度まで。漉き加工後の染色もできます。ご希望でしたら床面染色致します。
納期・・・ご注文お受けしてから、1週間~10日程度でお届け致します(送料別途)。
現在すぐにできる染料カラーは、黒、ブラウン、ネイビー、キャメル、イエロー、マゼンタです。
その他、随時増やしていきます。
各種顔色はご相談下さい。現在パールは、シルバー、ゴールド、グリーン、レッド、ブルーお受けしています。
パール顔彩、色混ぜ可能。
ご注文・・・お問い合わせフォームより、「○○な感じの色にしたいのですが」等メール下さい。
1営業日中に返信させて頂きます!
あなた色のニュアンスをお聞かせ下さい。あなただけの革作品の為に革をご用意致します。
-
仕上がった革の種類について

みなさんこんにちは。
ここまでで出来上がった革の一般的な性質について以下にまとめられます。
他の素材と比べ優れている性質。
①感触が優れている。柔らかさ、滑らかさなど。
②保湿性があり、触ると暖かく感じる。
③気温による変化が少ない。
④適度な可塑性、弾力をもつので、各種の形状に加工できる。靴、衣料、手袋として
露出しうる肌をしっかり保護できる性質がある。
⑤切り口は避けにくく、ほころびにくい。繊維として破れにくい素材である。
欠点としては以下があります。
①品質、形状が一定でなく、部位によって性質の違いがあり、裁断時の歩留りが悪く、
大きい面積の場合は均質な生地になりにくい。
②色落ちしやすい場合がある。染色堅牢度が低い。
③水濡れに弱い。
革特有の特徴として、親水性があり、空気中の水分がおおいとき、吸収し乾いていると放出します。
同時に革が膨潤、収縮するので、面積や体積が不安定になり形状変化しやすいです。この特徴は
皮本来の特徴に由来しますが、鞣し工程のところでも説明したとおり、革になっていくにつれ、
この欠点を補う特徴が付与されていきます。
それが優れた点になっていき、革の特徴になります。
仕上がった革は、以下のように分けられます。主なものだけまとめました。
1・銀付き革 原皮の本来の銀面模様をそのまま生かして仕上げてある革。代表的なものに
ボックスカーフがあります。仔牛皮を原料として、染色、タンパク質系バインダーで仕上げをして、
アニリン仕上げなど透明感のある仕上げがしてあります。靴、ハンドバック、鞄、家具など用途は
幅広いです。
2・ガラス張り革 クロム革製造工程で、ガラスに張り付けて乾燥して、銀面をバフィングして、
塗装仕上げした革です。原料は主に成牛皮。銀面が均一だが、風合いは銀付き革より劣ります。
3・スエード 革の床面をバフして、ベルベット状に起毛させて仕上げた革。仔牛の革から作られている
スエード革は高級品です。成牛皮から製造される場合、毛羽がやや長く、ベロアと呼ばれています。
4・バックスキン 鹿皮の銀面を除去して毛羽建てた皮。
5・ヌバック 革の銀面をバフして起毛させた革。スエードより、毛足がとても短くビロード状。スエード
革をさらに滑らかにしたような革です。
6エナメル革 パテントレザーともいわれています。革の銀面にワニス等を塗布、乾燥を繰り返し、光沢の
ある強い被膜を作って仕上げる。ハンドバック、靴の甲革などに使われます。
7・型押し革 革の銀面に種々の型を加熱、加圧して模様をつけた革。ハンドバック、ケースなどに
用いられます。
8・タンニン革 植物タンニン鞣しによって製造されたヌメ革。鞄、袋物、ベルト、革工芸など、タンニン
鞣しの特徴を生かして様々な用途に使用されます。
スエード、ベロア、バックスキン、ヌバックはどれも起毛革ですが、上記の違いがあります。
出来上がった革は、計量(大きさを測ります)、出荷され、なんらかの製品生地として活用されていきます。
もちろん、クラフトをされる方々にも販売されます。
ここまで、製革についてのご紹介読んで頂いた方、ありがとうございます。
結構すでにご存じの一般的な話も多かったかもしれませんが、仕立てる前の革の製造に、
ちょっとでもご興味を持って頂けたらと思いました。
今後は、もうちょっと、革でお作りの方に役立つ話題になればと思っています。
それでは!
-
製革の仕上げ、補助作業。

みなさんこんにちは。
製革の仕上げ塗装は、その前後で革に補助的に加工を施す時があります。
今日は、そちらをご紹介します。
①バフィング・・・銀面をサンドペーパーでバフ処理をして仕上げます。銀面の悪い革に行い、キズなどを
削り取って修正します。その後、塗装作業を行います。また、ヌバック、ベロアのような毛足のある表面処理
を行う際にも使われる処理です。
②ポリッシング・・・フェルト、砥石で革表面を摩擦、磨き上げます。平滑さを加え、目止めを行います。ナッパ
革(という柔軟性のある平滑な革)、衣料革、手袋、グローブ革の製作の工程で行われます。
③空うち(ミリング)・・・空のドラムの中で革を打ちほぐし、繊維をほぐして、革に柔軟性を与えます。またシボ
つけのため行われます。一般に衣料革によく用いられます。似た加工ですが、バタ振り(という革をバタバタ
振りおろす機械)によって柔軟性を付与することもあります。
④型押し・・・革の表面に凹凸模様を、圧力、熱で型押しする作業。銀面のキズ等を型押しで目立たなく
することができる。クロコダイルなど爬虫類の柄等イミテーション加工をする場合がある。
塗装前でも、後でも行える。金属ロールや圧力プレスで革に熱、圧力をかけ、加工する。
⑤シボつけ・・・銀面にしわをつける作業、銀面を折りたたんだり、またはポーティングマシンという機械で
シワをつけていく。シボには主に以下があります。
1・水シボ 波模様のシボ加工
2・角シボ 水シボに対してさらに縦方向にシワをつけた加工
3・八方もみ 角しぼにさらに両対角、つまり八方向にもみあげてシワをつけてある加工
これらの加工はベルト、鞄などに施されています。
⑥グレージング(ガラス掛け)・・・革の銀面に平滑性、光沢を付与するために、ガラス板、めのう、金属
ローラーで銀面に圧力を加えつつ摩擦します。主にカゼイン、アルブミン仕上げの革に施される加工。
⑦アイロンプレス・・・塗装工程中、後に革表面に平滑性、艶を与えるためにアイロンプレスをします。
合成樹脂仕上げの場合、革表面に均一で薄い塗膜を伸ばすことができます。熱の入った金属板の下に
革を敷いて、金属ロールを通過させて金属板にこすり付けます。
これらの作業は、レザークラフトされる方でも、設備がなくても手作業で行っている方もいるかも
しれません。染色してから、ガラス板で磨いたり、染める前に銀磨りする方はいるかと思います。
革は、仕上げ方によっても最終的に全く違った表情を見せますので、染色、加脂だけでなく、この仕上げ
が重要です。また機能性、耐久性、官能性、にダイレクトに影響します。ユーザーの好き嫌いが分かれるのも、
この仕上げによるところは大きくあると思います。
やっと仕上げまで終わりましたね!
ここまで、ざっとですが、製革の流れを原皮を取るところからご紹介してきました。私の説明では、
工場見学みたいなリアルさは伝わりませんが、製革のしくみが、革で作られる方に少しでも伝われば
幸いです。
次回は、革を使うに当たって知っておくといい、出来上がった革素材の性質をご紹介致します。
それでは!
-
革の仕上げ塗装方法
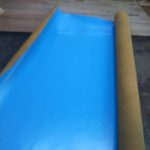
みなさんこんにちは。
今日は革の塗装作業について。
お客さんの要望はもちろんですが、タンナーさん、製革工場の設備によってもできることは違います。
以下の4つの方法を色々組み合わせることによって製革の仕上げが行われます。
①刷毛塗り・・・刷毛を用いた仕上げ塗装は植物タンニン革、豚革、銀磨り革、床革など、表面の凹凸が
大きい革、毛穴の深い革の塗装に用いられます。革表面の状態に応じて毛足の長さを選択して塗装を行い
ます。一人または二人で行い、当社では、私、または私と社長で行います。出来るだけ素早く仕上げ用顔料
や配合液を革全体に均一に塗布して刷毛ムラがないようにします。
スプレー塗装の下塗り時にも行います。
②スプレー吹付・・・最も一般的に行われている方法です。圧縮空気をスプレーガンに通し、空気が吐出する
時の圧力を利用して塗装液を革に塗布していきます。手吹き、ロータリー式(回転式)が一般的。ロータリー式
は複数個スプレーガンが設置されたロータリー吹付器下をベルトコンベアに載った革が移動します。溶剤や
塗料液の液量調整、コンベアの速度を機械的に管理できます。
手吹き式は手作業で染料、顔料、溶剤などをスプレーガンボトルにそれぞれ必要時にいれて塗布していきます。
当社はこちらです。
③カーテン塗装・・・均一な液量をカーテン状にして下に落下させていく機械を用いて、その下を革が、一定速度
で移動していくことで、塗装が行われます。常に一定量の塗料を革表面に塗装していく方法に適しています。
エナメル仕上げ塗装などに適しています。塗膜が薄く、柔軟な革の塗装にはあまり適していません。
④ロール塗装・・・ロールコーターマシンという機械を使用します。溝ロールに塗料を含ませて革表面と
接触、回転させ、塗料を革表面に塗布する方法です。ロールの硬度、溝の深さ、押し付け圧力などで、
塗膜の厚さを調節します。
当社は、こじんまりやっていますので、①、②の刷毛塗り、手吹きスプレーガンによる染色塗装を行っています。
現在は小ロットが主で、一日の吹付作業、大体半裁を10~15枚程度がマックスです。毎日やるわけでは
ないので、特に天気が良い日を選んで、週に1回くらいの頻度で行います。
刷毛塗り、吹付けに乾燥を挟みながら行いますので、開始から数日をかけて行っています。
小さいロットでは、このところは、個人で副業などで革製品を作る方がいらっしゃるので、
その方からご相談があった場合、少量50デシ~100デシ位量の革を染色します。
当社設備では丘染めになります。
作業方法書いてきましたが、革の仕上げ塗装の際、その前後に行う補助作業があります。
その色々な作業について次回紹介します。レザークラフトをされる方にもご参考になることも
あるかと思います。
それでは!