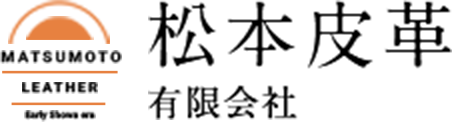2020年6月
- 新着情報
-
姫路からヌメ革入荷中。
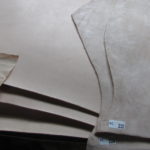
当社取引先の兵庫県姫路市のタンナーさんから、ヌメ革仕入れ中です。
生成り、素上げ革です。
素上げ革から、染色、カービング等ご自分でプレーン素材の革づくりから製作したい方はおすすめです。
例)革の背中→腹、短冊形状に30センチ幅カット 約30デシならで1デシ80円程度。
送料は別途。
元厚2・3~2.5ミリです。
その他ご希望の大きさ、欲しい部位、相談させて頂きます。
ご希望の厚みに加工して販売致します。革漉き代は無償。
例)背中→腹 短冊カット30センチ×約100センチでご購入、背中側から下50㎝を1.5ミリ 残りを1.0ミリ等
ご要望に応じて漉き分け可能。
しっかりした床革が出た場合、ご希望でしたら一緒にお渡し致します。
不要の場合は当社にて有効活用致します。
ご希望の方はお手数ですが、お問い合わせメールフォームよりご連絡下さい。
在庫ヌメ革画像を送ります。
よろしくお願い致します。
-
酸性染料について。

みなさんこんにちは。
キャメル小さく染めた時の写真です。
今日も染料の話です。
皮革において一番重要なのは酸性染料です。使用されている大半の染料がこれに当たる
からです。弱酸性溶液中で染色できることからこの名称で呼ばれていますが、
以下に大きく分かれます。
①均染・浸透型・・・染料の吸じんを強くするため強めの酸性PH3~4位で色を吸じんさせて染色します。
ベースとしてこちらを浸透、染着させて、
②表面染着型・・・こちらを使って色の表面濃度を高くします。PH5~6で染料を吸じんさせます。
こちらは、湿潤状態では少し色落ちがおこります。
両方を使って染色し、加脂をしたら、一度水洗い(ソービング=表面に残った色を落とします)
その後、テンション乾燥します。
他に③金属塩錯体染料、があります。含金染料ともいいます。耐光性、湿潤堅牢性はかなり高い染料です。
色はそれぞれありますが、暗めの色調の染料で、金属塩がタンパク質と錯体を形成するのを利用しています。
もう一つ、直接染料というのもあります。
そのままで染着が強いものがありますが、多くは酸を添加することで安定化します。上記の酸性染料より
色がハッキリしているものが多いのが特徴ですが、表面に色が入る、表面染着型の染料といえます。
大体、①~②で染めていくのですが、②の工程では、塩基性染料を使うことがあります。
クロム革には中性、タンニン革では酸性溶液を用意して染着させます。上掛け染料として
使用して、こちらも特徴である発色の良さを出していきます。耐光性は弱いのですが、
染めた時の発色はいいです。
経年変化ですぐに色があせてくる場合はこの染料の可能性もあります。
ただ、製品だけを見てどういう工程でその生地が出来たかを知るのは困難です・・・。
他色々な性質の染料がありますが・・・、ほとんど上記の染料の製品(革)と考えていいかと思います。
特徴的なものでは、ホルマリン鞣し後の鹿革で使う、建染染料があります。
いわゆる藍染め、インジゴ染料として使われています。空気に触れないように丁寧に揺らして染めて
その後空気にさらして酸化発色させるってのを繰り返します。
個人的に興味あるのが、天然染料なのですが、植物から抽出した染料で、皮革用ではヘマチンといって
ログウッドから得られる染料が有名です。鉄、チタンで媒染してちょっと青味の入った黒色になります。
他にも天然染料はたくさんあります。
ただ、革に色を定着させていくにはそれなりの量が必要になってきます。
リクエストがありましたら小さく染めていくのを始めています、が、
まだまだ修行中ではあります。
みなさんのイメージを具現化できるようもっと練習しますね。
それでは!
-
皮革染料と革。

みなさんこんにちは。
革の染色について今日から書いていきます。
まず大きくお伝えしたいのですが、染色とは染料を用いて色を繊維に染みこませていくことです。
対して顔料による着色は革の表面に色を乗せることです。
これは、工程としては仕上げ作業に属するものとして捉えることができます。
顔料でもある程度革に色素は染みこんでいますが、染料と比較すると色が革表面に乗っているイメージです。
染料では革の地の色が出やすいです。対して顔料はあまり地の色の影響を受けません。
で、ここからしばらくは、「染料」による「染色」の話をしていきます。
ここしばらく革繊維と鞣剤、の反応の話をしていたのですが、染色になって、今度は染料と革繊維の
相互作用の話になってきます。革繊維と染料の間になんらかの結合が生じると「色が染まる」ということに
なります・・・。
なので、染色先になる革の特徴を理解しつつ、それに応じた染料を選択しなければ、革への浸透性、
均染性、適度な濃度、色の堅牢性を持ち得ることはできません。
染料は、種類は色でもちろん示されているのですが、同時に、化学構造、染色基質(染めるものの種類)
染色方法、使用の目的なんかが明記されています。皮革用、というか、薬剤、染料業者さんに革素材に
合う染料を提案してもらいます。染料の化学構造が基質の革と相性のよいものでなくては、染まりません。
皮革染料の大半は、アニオン染料と言われるものです。アニオン?説明しますと、負に荷電したイオンの
ことです。つまり陰イオンです。これに対して陽イオンはカチオンといいます。
染色基質の革に関して。一般にクロム革は陽イオン基質です。タンニン革は陰イオン基質が強めです。
陽イオンは電子を出す性質、陰イオンは電子を入れる性質を持ちます。
つまりお互い結合しやすい性質を持ちます。
ですから、クロム革はアニオン性、タンニン革はカチオン性染料との相性がいいのですが、
タンニン革でも、クロム塩やアルミニウム塩で媒染処理(前処理としておきます)をしておくことで、
染色が可能です。アニオン性酸性染料で染色する場合、この処理をします。
このように、染色の為、革基質に処理を行うこともあります。アニオン染色は革の染色で、
最も多く用いられる染色法で、酸性染料などの合成染料を用いて、色が濃く堅牢な染色が出来ます。
カチオン染色は色調は鮮やかですが、日光堅牢度に弱い場合があります。こちらも合成染料が主流です。
ちなみに合成染料って化学構造としてアゾ系って呼ばれていて、合成染料の大半がこの形状を持ちます。
酸性染料はクロム革の染色に最も広く使用されています。
皮革染料は、酸性染料、直接染料を含むアニオン染料が9割以上で、ほとんどが合成染料。
染料を定着させのるに、どんな素材もそれなりの化学処理はなされているでしょう。
革も同じ。
今日はここまで。
結構、細かくやっていますが、次回から酸性染料~ほかの染料についてもしくみを紹介していきますね!